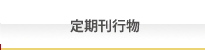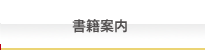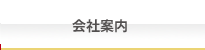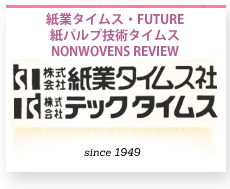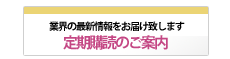新たな発展期を迎える紙パルプ~循環型産業150年で培われた創造性と対応力~
我が国で近代製紙業が興ってから2024年は150年という節目の年であった。これを記念して「紙の博物館」をはじめ各方面でさまざまなイベントが開催され、25年7月には20年ぶりとなる新しい日本銀行券が発行され、その新壱万円札には近代製紙業の生みの親である渋沢栄一翁の肖像が採用されている。
日本の製紙業は現在、151年目の歩みを始めているところだが、その記念すべき年に当社は創業75周年を迎える。製紙産業150年のうち、半分を業界とともに共有してきたことになるが、それを記念し当社では単行本『新たな発展期を迎える紙パルプ~循環型産業150年で培われた創造性と対応力~』を発刊した。
紙は森林から生まれる。森林はCO2を吸収して地球温暖化を防ぎ、水資源を涵養して自然災害のリスクを下げ、人々に憩いと安らぎの場を提供するなど多面的な機能を備えている。そして、その持続可能な利用を通じて森林資源の循環と再生を支えているのが製紙産業である。しかも一度、役割を終えた紙の3分の2近くは古紙として再利用されており、森林の恵みを少しも無駄にすることなく、それぞれの企業や団体が事業を営んでいる。
同書では、151年目に入った紙パルプ産業の到達点を検証し未来を展望するため、巻頭では東京大学名誉教授・尾鍋史彦先生による特別寄稿で「これまで」を総括するとともに「これから」を展望、また各種団体や主要各社の取組みと今後の方向性を当事者の証言・肉声によって幅広く紹介、令和時代の指針・教訓として広く関連各界に提供する企画とした。

151年目に入った日本の紙パルプ産業の到達点を検証し未来を展望する。
B5判・本文288頁
定価 11,000円(税込・送料別)
2025年6月25日
本書の内容
─ 特別寄稿 ─
●紙パのこれまでとこれから
尾鍋史彦(東京大学名誉教授)、日本印刷学会元会長 Beyond 2025の製紙産業の サステナビリティーに向けた新たな挑戦
─ 有識者インタビュー ─
●業界リーダーの視点
野沢徹(日本製紙連合会)製紙産業には強みがあるバイオリファイナリーへの挑戦
長谷川一郎(古紙再生促進センター)日本は今後も紙リサイクルの優等生であり続ける
大久保信隆(全国製紙原料商工組合連合会)古紙の商売は「不易流行」、原産地証明で持ち去り防止を
瀬田章弘(全日本印刷工業組合連合会)CSR経営を一丁目一番地として地域社会の課題に取り組む
黒田章祐(日本紙製品工業組合)これからの教育に必要なのは多様性の尊重
●企業トップに聞く
野沢徹(日本製紙)炭素を固定して循環させるビジネスが重要になる
川本洋祐(レンゴー)従業員が「いい会社だな」と思える会社づくりを目指す
松田裕司(特種東海製紙)他社が真似できないオンリーワンビジネスを構築する
北村貴則(大和板紙)利益を確保し「あと10年で給料を倍にする」と宣言
佐野武男(丸富製紙)メーカーの原点に戻ったものづくり 消費者の立場と環境を意識
井川博明(カミ商事)スピード感を持って新たな柱を模索 新規需要の創造を追求する
渡辺昭彦(日本紙パルプ商事)ワークエンゲージメントを高めスパイラルアップする理想的なサステナブルな企業の姿を実現する
田辺円(KPPグループホールディングス)経営陣は社員のロールモデル、先頭に立っての行動が求められる
三瓶悦男(新生紙パルプ商事)自らの意識を変えて需要構造の変化に対応する
竹尾稠(竹尾)文化としての「紙」を守り、未来に向け発展させていく
清家義雄(平和紙業)「世のため人のため」という社是はこれからも変わらない
藤井章生(レイメイ藤井)創業以来の当社の基盤 「紙」はこだわりを持って取り組む
梅田愼也・伊藤智織(宮崎)国内製紙工場への供給第一 基本に忠実に仕事を持続する
野上哲彦(IHIフォイトペーパーテクノロジー)“待ちの姿勢”から寄り添った問題解決の提案へ
山下宏(バルメット)多様性のある国際的サプライヤーとして変化の下で求められる最新技術を提供
戸田訓人(小林製作所)独自技術で板紙・特殊紙・フィルム分野を開拓 ユーザーとの協業に応える技術力を
藤田和巳(相川鉄工)社会の資源リサイクルに協力し新事業の柱へ サーキュラーエコノミーで欠かせない企業に
篠原貴裕(川之江造機)変化の激しい時こそチャンス今こそ「ともに」を体現する
加藤雄一朗(日新化学研究所)生産性・安定操業・品質改善に貢献し酵素やCNFなどの天然原料も積極活用
─ 巻末資料 ─
『紙業タイムス年鑑』に見るこの10年(2015〜24年)